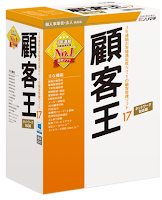日本NPOセンター編集・発行、2012年4月発行(第4版)、A5判、70P、540円(税込)
「NPOについて講座をするけれど、手ごろな教材はないか?」、「NPOを立ち上げる人に、必ず伝えなければならないことは?」、「短い時間でNPOが解る本は?」こんなことをお考えの方に好評の1冊です。ブックレット『知っておきたい NPOのこと』は、日本NPOセンターが各地の支援センターと協力して作成した、「信頼されるNPOの7つの条件」と、WebサイトNPO広場で公開中の「NPO基礎知識Q&A」を再編集して作成したものなので、現場でのノウハウが凝縮された、「知りたい」・「教えたい」ツボを押さえた内容になっています。増補版では新たに新公益法人制度の解説も加えました。ぜひ、この1冊をお手元に置いて、ご活用ください。各種講座・講義など多数お求めの場合は、割引価格でご購入いただけます。またNPO支援センター向けにも特別価格を設定しています。
●ご注文・お問合せ
メール info@hnposc.net
TEL:011-200-0973 FAX:011-200-0974
月~金曜日10:00~18:00
「書名・冊数・お送り先」を添えてお申込みください。
2016-03-31
広がれ!まちぢから
さっぽろまちづくり隊Ⅲ実行委員会(委員長:樽見弘紀北海学園大学法学部教授、事務局:北海道NPOサポートセンター)では、地域住民がボランティア活動や体験活動を通じて地域の課題に取り組むことで、住民同士が「学びあい、支えあう」地域のきずなづくりの取り組みを札幌市内5 地区で実施しました。
■本郷通~イベントで広げる:本郷通商店街萬蔵祭などで商店街イベント企画
■麻生~歴史で広げる:亜麻そば祭りへの参加、親子で亜麻パン作りなど体験活動や三世代交流
■中の島~ボランティアで広げる:商店街・町内会と協力して地域の夏祭りやクリスマス会でボランティア活動
■琴似~アートで広げる:住民参加の演劇「オシャレな果実」公演を通じて地域交流
■狸小路~情報で広げる:サブカルチャーの拠点で情報発信やまち歩きをしながら映像撮影
■発行・編集さっぽろまちづくり隊Ⅲ実行委員会■B5判 32ページ
■内容第1 章 発掘!まちぢから第2 章 まちぢからを広げる(書籍は無料ですが別途送料が必要です。)
●ご注文・お問合せ
メール npo@mb.infosnow.ne.jp
TEL:011-200-0973 FAX:011-200-0974
月~金曜日10:00~18:00
「書名・冊数・お送り先」を添えてお申込みください。
■本郷通~イベントで広げる:本郷通商店街萬蔵祭などで商店街イベント企画
■麻生~歴史で広げる:亜麻そば祭りへの参加、親子で亜麻パン作りなど体験活動や三世代交流
■中の島~ボランティアで広げる:商店街・町内会と協力して地域の夏祭りやクリスマス会でボランティア活動
■琴似~アートで広げる:住民参加の演劇「オシャレな果実」公演を通じて地域交流
■狸小路~情報で広げる:サブカルチャーの拠点で情報発信やまち歩きをしながら映像撮影
■発行・編集さっぽろまちづくり隊Ⅲ実行委員会■B5判 32ページ
■内容第1 章 発掘!まちぢから第2 章 まちぢからを広げる(書籍は無料ですが別途送料が必要です。)
●ご注文・お問合せ
メール npo@mb.infosnow.ne.jp
TEL:011-200-0973 FAX:011-200-0974
月~金曜日10:00~18:00
「書名・冊数・お送り先」を添えてお申込みください。
2016-03-30
「さっぽろまちセンガイド-入門編-」
町内会などの地域団体と、あるミッションの元に人が集まり活動するNPO、そしてさまざまな世代の市民。地域に生きるこれらの人々が顔を合わせ、ともにまちづくりについて話し、学び合うため、様々な場所で「三世代交流でまちづくり」をテーマにワークショップを開催しました。会場は、地域に根付いた、市民の手作りによる、地域のコミュニティスペース。そして、将来に向けて市民の継続的な利用が可能な場として、札幌市が概ね中学校区(人口約2万人)をベースに設置する「まちづくりセンター」(以下「まちセン」)にも注目しました。
市民がまちセンを上手に利用し、まちづくり生涯学習を進めていくための第一歩として、まず、もっと多くの市民がまちセンの存在を知る必要があると感じ、この度、「さっぽろまちセンガイド -入門編-」を作成しました。このハンドブックで、みなさんが「まちセン」の存在を知って、人や地域との出会いの場所として、もっともっと利活用するきっかけが作れたら幸いです。*A5版変形24頁
●ご注文・お問合せ
メール info@hnposc.net
TEL:011-200-0973 FAX:011-200-0974
月~金曜日10:00~18:00
「書名・冊数・お送り先」を添えてお申込みください。
市民がまちセンを上手に利用し、まちづくり生涯学習を進めていくための第一歩として、まず、もっと多くの市民がまちセンの存在を知る必要があると感じ、この度、「さっぽろまちセンガイド -入門編-」を作成しました。このハンドブックで、みなさんが「まちセン」の存在を知って、人や地域との出会いの場所として、もっともっと利活用するきっかけが作れたら幸いです。*A5版変形24頁
●ご注文・お問合せ
メール info@hnposc.net
TEL:011-200-0973 FAX:011-200-0974
月~金曜日10:00~18:00
「書名・冊数・お送り先」を添えてお申込みください。
2016-03-24
ソリマチ 顧客王17特別販売のご案内
北海道NPOサポートセンター × ソリマチ(株)による
NPO法人のための顧客管理ソフト(寄付金・会員管理と会費管理)顧客王17特別販売のご案内
会員・顧客管理、会費と寄付管理、個人情報などキチンと管理出来ていますか?2016年 5/31(火)までの特別販売
(1)1年間無料サポート付き (2)NPO法人向けテンプレート搭載
定価¥30,000円の所 → ¥20,000円で販売しております。
さらにに現在キャッシュバックキャンペーン実施中の為、購入後ユーザー登録とキャンペーン登録をすると¥10,000円引きになりますので、
実質¥10,000円で購入可能です。
※キャンペーン価格は5/31まで。要ユーザー登録及び、WEB申込が必要です。
NPO法人が顧客王17で出来る主な事!買ってすぐ使える簡単顧客管理ソフト顧客王17とは。
(1)NPO法人向けテンプレートでらくらく導入!実際のNPO法人が会員の管理に使っている項目がすぐに使えるので簡単に導入できます。
(2)寄付金管理と履歴・会員管理と会員会費管理も簡単。寄付金や会費の入金管理、イベントへの参加実績など履歴も自由に登録・管理が可能です。また、寄付金、会員向けにDM、メール送信も出来ます。
●顧客王17のカタログがダウンロード出来ます。※購入希望の方は、北海道NPOサポートセンターまでお気軽にお問い合せください。
 携帯・スマホをご利用の場合左側QRコードからご注文も可能です。
携帯・スマホをご利用の場合左側QRコードからご注文も可能です。
●問い合わせ
北海道NPOサポートセンター
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東3丁目LC北六条館6F
電話:011-299-6940 FAX:011-299-6941
NPO法人のための顧客管理ソフト(寄付金・会員管理と会費管理)顧客王17特別販売のご案内
会員・顧客管理、会費と寄付管理、個人情報などキチンと管理出来ていますか?2016年 5/31(火)までの特別販売
(1)1年間無料サポート付き (2)NPO法人向けテンプレート搭載
定価¥30,000円の所 → ¥20,000円で販売しております。
さらにに現在キャッシュバックキャンペーン実施中の為、購入後ユーザー登録とキャンペーン登録をすると¥10,000円引きになりますので、
実質¥10,000円で購入可能です。
※キャンペーン価格は5/31まで。要ユーザー登録及び、WEB申込が必要です。
NPO法人が顧客王17で出来る主な事!買ってすぐ使える簡単顧客管理ソフト顧客王17とは。
(1)NPO法人向けテンプレートでらくらく導入!実際のNPO法人が会員の管理に使っている項目がすぐに使えるので簡単に導入できます。
(2)寄付金管理と履歴・会員管理と会員会費管理も簡単。寄付金や会費の入金管理、イベントへの参加実績など履歴も自由に登録・管理が可能です。また、寄付金、会員向けにDM、メール送信も出来ます。
●顧客王17のカタログがダウンロード出来ます。※購入希望の方は、北海道NPOサポートセンターまでお気軽にお問い合せください。
 携帯・スマホをご利用の場合左側QRコードからご注文も可能です。
携帯・スマホをご利用の場合左側QRコードからご注文も可能です。●問い合わせ
北海道NPOサポートセンター
〒060-0906 北海道札幌市東区北6条東3丁目LC北六条館6F
電話:011-299-6940 FAX:011-299-6941
2016-03-02
2/27(土)「ささえあいまちづくりフォーラム」~住民主体の支え合いのあるまちづくり~報告
2月27日(土)13:30より札幌市民ホールにて、参加者、関係者48名にて「ささえあいまちづくりフォーラム」~住民主体の支え合いのあるまちづくり~と題し、NPO法人市民福祉団体全国協議会の田中尚輝氏をお招きし、「介護保険と生活支援サービスの具体的展開について」お話いただきました。
介護保険制度改正に伴う、新しい地域支援事業において制度の中に地域住民の助け合いや交流活動、ボランティア・市民活動団体・NPO等による様々なサービスが位置付けられ、住民相互の支え合いや助け合いがまちづくりの基本となり、協議体・生活支援コーディネーターが地域に必要なサービスを創出しながらネットワークを構築していく仕組みづくりが求められることとなりました。
このフォーラムでは、新制度についての理解を深め、誰もが地域で尊厳ある暮らしを実現できるよう、課題を共有し、担い手として札幌の事業所や地域の住民に何ができるか一緒に考えるというテーマで講演者の田中尚輝氏氏にお話しいただきました。また函館市の「生活支援コーディネーターの役割と生活支援サービス」と題して、丸藤 競氏による函館市の事例として、高齢者人口の現状や、生活支援コーディネーターとしての連携や役割等を発表いただきました。※当日発表いただいた丸藤氏の未配付パワーポイントについては、こちらからダウンロードいただく事が出来ます。
さらにパネルディスカッションでは「生活支援サービスに期待されること」と題して、認定NPO法人シーズネット 代表 奥田 龍人氏、NPO法人たすけあいワーカーズのほろ 代表 井端 幸子氏も加わり、表題にて今後の生活支援サービスの担い手の課題や提案が話し合われました。
介護保険制度改正に伴う、新しい地域支援事業において制度の中に地域住民の助け合いや交流活動、ボランティア・市民活動団体・NPO等による様々なサービスが位置付けられ、住民相互の支え合いや助け合いがまちづくりの基本となり、協議体・生活支援コーディネーターが地域に必要なサービスを創出しながらネットワークを構築していく仕組みづくりが求められることとなりました。
このフォーラムでは、新制度についての理解を深め、誰もが地域で尊厳ある暮らしを実現できるよう、課題を共有し、担い手として札幌の事業所や地域の住民に何ができるか一緒に考えるというテーマで講演者の田中尚輝氏氏にお話しいただきました。また函館市の「生活支援コーディネーターの役割と生活支援サービス」と題して、丸藤 競氏による函館市の事例として、高齢者人口の現状や、生活支援コーディネーターとしての連携や役割等を発表いただきました。※当日発表いただいた丸藤氏の未配付パワーポイントについては、こちらからダウンロードいただく事が出来ます。
さらにパネルディスカッションでは「生活支援サービスに期待されること」と題して、認定NPO法人シーズネット 代表 奥田 龍人氏、NPO法人たすけあいワーカーズのほろ 代表 井端 幸子氏も加わり、表題にて今後の生活支援サービスの担い手の課題や提案が話し合われました。
2016-02-01
2/27(土)13:30~開催 「ささえあいまちづくりフォーラム」~住民主体の支え合いのあるまちづくり~のご案内(市民協研修会2015年度)
介護保険制度改正に伴う新しい地域支援事業において、制度の中に地域住民の助け合いや交流活動、ボランティア・市民活動団体・NPO等による様々なサービスが位置付けられました。
住民相互の支え合い、助け合いがまちづくりの基本となり、協議体・生活支援コーディネーターが地域に必要なサービスを創出、ネットワークを構築していく仕組みです。制度についての理解を深め、誰もが地域で尊厳ある暮らしを実現できるよう、課題を共有し、担い手として何ができるか一緒に考える場としたいと思います。ぜひご参加ください。
●主催:NPO法人市民福祉団体全国協議会
●共催:NPO法人北海道NPOサポートセンター
●後援:全国労働者共済生活協同組合連合会、北海道(予定)
●対象:北海道内で活動する市民活動団体、ボランティア団体、NPO法人等
●日時:2016年2月27日(土)13:30~16:20
●会場:札幌市民ホール 会議室1
●定員:60人(先着順)※参加費:500円(資料代)
●申込・問い合わせ先:NPO法人福祉NPO支援ネット北海道
FAXまたはEメールに氏名、所属先及び連絡先を書いてお申込みください。e-mailの件名は「ささえあいフォーラム申込」と記載ください。
なおFAXでお申込の場合、左上チラシをクリックし、裏面の申込用紙をプリントアウトして必要事項記載の上、FAX送信をお願いいたします。
FAX:011-795-2664 TEL:011-712-8333 (NPO法人福祉NPO支援ネット北海道)
Eメール:sapporo-kaigo@npo-hokkaido.org
プログラム:基調講演
「介護保険と生活支援サービスの具体的展開について」NPO法人市民福祉団体全国協議会 田中 尚輝 事例発表「生活支援コーディネーターの役割と生活支援サービス」函館市地域交流まちづくりセンター長 丸藤 競氏
パネルディスカッション「生活支援サービスに期待されること」
パネリスト:NPO法人シーズネット 代表 奥田 龍人氏
NPO法人たすけあいワーカーズのほろ 代表 井端 幸子氏
コメンテーター 函館市地域交流まちづくりセンターセンター長 丸藤 競氏/コーディネーター:田中 尚輝氏
住民相互の支え合い、助け合いがまちづくりの基本となり、協議体・生活支援コーディネーターが地域に必要なサービスを創出、ネットワークを構築していく仕組みです。制度についての理解を深め、誰もが地域で尊厳ある暮らしを実現できるよう、課題を共有し、担い手として何ができるか一緒に考える場としたいと思います。ぜひご参加ください。
●主催:NPO法人市民福祉団体全国協議会
●共催:NPO法人北海道NPOサポートセンター
●後援:全国労働者共済生活協同組合連合会、北海道(予定)
●対象:北海道内で活動する市民活動団体、ボランティア団体、NPO法人等
●日時:2016年2月27日(土)13:30~16:20
●会場:札幌市民ホール 会議室1
●定員:60人(先着順)※参加費:500円(資料代)
●申込・問い合わせ先:NPO法人福祉NPO支援ネット北海道
FAXまたはEメールに氏名、所属先及び連絡先を書いてお申込みください。e-mailの件名は「ささえあいフォーラム申込」と記載ください。
なおFAXでお申込の場合、左上チラシをクリックし、裏面の申込用紙をプリントアウトして必要事項記載の上、FAX送信をお願いいたします。
FAX:011-795-2664 TEL:011-712-8333 (NPO法人福祉NPO支援ネット北海道)
Eメール:sapporo-kaigo@npo-hokkaido.org
プログラム:基調講演
「介護保険と生活支援サービスの具体的展開について」NPO法人市民福祉団体全国協議会 田中 尚輝 事例発表「生活支援コーディネーターの役割と生活支援サービス」函館市地域交流まちづくりセンター長 丸藤 競氏
パネルディスカッション「生活支援サービスに期待されること」
パネリスト:NPO法人シーズネット 代表 奥田 龍人氏
NPO法人たすけあいワーカーズのほろ 代表 井端 幸子氏
コメンテーター 函館市地域交流まちづくりセンターセンター長 丸藤 競氏/コーディネーター:田中 尚輝氏
2/20(土)13:30~生活困窮者自立支援法を考える市民の集いのご案内
2/20(土)13:30~生活困窮者自立支援法を考える市民の集い(参加費無料)
2015年4月から本格実施された生活困窮者自立支援法は、困窮者に寄り添った支援をうたっています。私たち北海道社会的事業所支援機構は、施行される前からこの法に大きな関心と危惧の念を抱いていました。それは、入り口としての相談体制はあっても、出口である就労場の確保や就労支援の内容が不透明な内容であると感じてきたからであります。
施行から1年を迎えようとするなか、本制度がどのような効果を上げ、また制度上の問題や相談者の課題等がどのように浮かび上がっているのか、それらの問題や課題等をどう解決していくべきかを、参加者と一緒に考えていきたいと思います。ふるってご参加ください。
■日時:2月20日(土)13:30~16:30(開場13:00)
■会場:北海道自治労会館3階中ホール(札幌市北区北6西7)
■定員:150人 ※事前申込必要(定員になり次第締切)
<お話しをいただく予定の皆さん>
■自治体の取り組みと今後の課題■
・北海道保健福祉部福祉局福祉援護課課長 菊池 崇さん
・札幌市保護自立支援課自立支援事業担当係長 及川 貴史さん
■相談事業者から見えた事、今後の制度上の課題■
・札幌市生活就労支援センターステップ主任相談支援員 佐藤真貴子さん
・コミュニティワーク研究実践センター常任理事 穴澤 義晴さん
・自立支援事業所ベトサダ 事務局長 藤原 聖巳さん
・ワーカーズコープ北海道事業本部 下村 朋史 さん
■参加費:無料
■主 催:*北海道社会的事業所支援機構、連合北海道
■協 賛:*札幌障害者活動支援センターライフ、共同連北海道ブロック会議、*北海道NPOサポートセンター、*北海道ワーカーズコレクティブ連絡協議会、*コミュニティワーク研究実践センター、*創生もえぎ、*ワーカーズコープ北海道事業本部、*自立支援事業所ベトサダ(*=特定非営利活動法人)
■お申込方法:FAX011‐613‐9323 申込メールhonbu@npolife.net
FAX、またはE-メールに、(1)団体名/(所属していない方は無記入で構いません)
(2)お名前(3)ご住所(4)連絡先(携帯番号、所属先TELなど)を明記の上お申込下さい。メールで申込の際は件名に「生活困窮者自立支援法を考える市民の集い参加希望」と明記ください。
●問い合わせ・連絡先:NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ/担当・石澤
札幌市西区琴似2条5丁目3-5 E-mail:honbu@npolife.net
TEL:011‐633‐6666 FAX:011‐613‐9323
又は、NPO法人北海道社会的事業所支援機構(NPOサポートセンター内)
TEL:011‐299-6940気付
2015年4月から本格実施された生活困窮者自立支援法は、困窮者に寄り添った支援をうたっています。私たち北海道社会的事業所支援機構は、施行される前からこの法に大きな関心と危惧の念を抱いていました。それは、入り口としての相談体制はあっても、出口である就労場の確保や就労支援の内容が不透明な内容であると感じてきたからであります。
施行から1年を迎えようとするなか、本制度がどのような効果を上げ、また制度上の問題や相談者の課題等がどのように浮かび上がっているのか、それらの問題や課題等をどう解決していくべきかを、参加者と一緒に考えていきたいと思います。ふるってご参加ください。
■日時:2月20日(土)13:30~16:30(開場13:00)
■会場:北海道自治労会館3階中ホール(札幌市北区北6西7)
■定員:150人 ※事前申込必要(定員になり次第締切)
<お話しをいただく予定の皆さん>
■自治体の取り組みと今後の課題■
・北海道保健福祉部福祉局福祉援護課課長 菊池 崇さん
・札幌市保護自立支援課自立支援事業担当係長 及川 貴史さん
■相談事業者から見えた事、今後の制度上の課題■
・札幌市生活就労支援センターステップ主任相談支援員 佐藤真貴子さん
・コミュニティワーク研究実践センター常任理事 穴澤 義晴さん
・自立支援事業所ベトサダ 事務局長 藤原 聖巳さん
・ワーカーズコープ北海道事業本部 下村 朋史 さん
■参加費:無料
■主 催:*北海道社会的事業所支援機構、連合北海道
■協 賛:*札幌障害者活動支援センターライフ、共同連北海道ブロック会議、*北海道NPOサポートセンター、*北海道ワーカーズコレクティブ連絡協議会、*コミュニティワーク研究実践センター、*創生もえぎ、*ワーカーズコープ北海道事業本部、*自立支援事業所ベトサダ(*=特定非営利活動法人)
■お申込方法:FAX011‐613‐9323 申込メールhonbu@npolife.net
FAX、またはE-メールに、(1)団体名/(所属していない方は無記入で構いません)
(2)お名前(3)ご住所(4)連絡先(携帯番号、所属先TELなど)を明記の上お申込下さい。メールで申込の際は件名に「生活困窮者自立支援法を考える市民の集い参加希望」と明記ください。
●問い合わせ・連絡先:NPO法人札幌障害者活動支援センターライフ/担当・石澤
札幌市西区琴似2条5丁目3-5 E-mail:honbu@npolife.net
TEL:011‐633‐6666 FAX:011‐613‐9323
又は、NPO法人北海道社会的事業所支援機構(NPOサポートセンター内)
TEL:011‐299-6940気付
2016-01-29
復興庁「県外自主避難者等への情報支援事業(平成27年度)」
平成27年度 第4回ニュースレター避難元ニュースレター (1/28発送)
● 皆さまからお寄せいただいた質問・要望について
● 相談窓口のご案内
● 避難元・避難先地域の新着情報
○ 総合目次
○ 福島県・県内市町村等からの広報紙
(情報対象期間 平成27年10月21日~平成28年1月12日※1)
○ 福島県・県内市町村等のその他ホームページ新着情報※2 福島県・県内市町村等
○ 北海道・道内市町村等のその他ホームページ新着情報 避難先地域
(情報対象期間 平成27年10月21日~平成28年1月12日)
※1 作業の都合上、一部の掲載する情報の公表時期が、上記の情報対象期間と異なる場合がございます。
※2 福島県・県内市町村等のホームページから収集した情報を、取りまとめてお送りいたします。内容は冊子の表紙にてご確認ください。
※3 ご自身が避難されている地域の広報紙、自治体ホームページ等から収集した情報をお送りいたします。
● 皆さまからお寄せいただいた質問・要望について
● 相談窓口のご案内
● 避難元・避難先地域の新着情報
○ 総合目次
○ 福島県・県内市町村等からの広報紙
(情報対象期間 平成27年10月21日~平成28年1月12日※1)
- 帰還・生活再建に向けた総合的な支援策について 福島県 PDF
- ふれあいニュースレター 第59号 政府原子力被災者生活支援チーム PDF
- 放射線対策ニュース 第36号 福島市 PDF
- 二本松市災害対策本部情報 第96号 二本松市 PDF
- 広報もとみや号外 No. 60 本宮市 PDF
- 復興情報 第92号 国見町 PDF
- 川俣町災害対策本部からのお知らせ No.145 川俣町 PDF
- 無料個別相談会開催のご案内 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 PDF
○ 福島県・県内市町村等のその他ホームページ新着情報※2 福島県・県内市町村等
○ 北海道・道内市町村等のその他ホームページ新着情報 避難先地域
(情報対象期間 平成27年10月21日~平成28年1月12日)
※1 作業の都合上、一部の掲載する情報の公表時期が、上記の情報対象期間と異なる場合がございます。
※2 福島県・県内市町村等のホームページから収集した情報を、取りまとめてお送りいたします。内容は冊子の表紙にてご確認ください。
※3 ご自身が避難されている地域の広報紙、自治体ホームページ等から収集した情報をお送りいたします。
登録:
コメント (Atom)